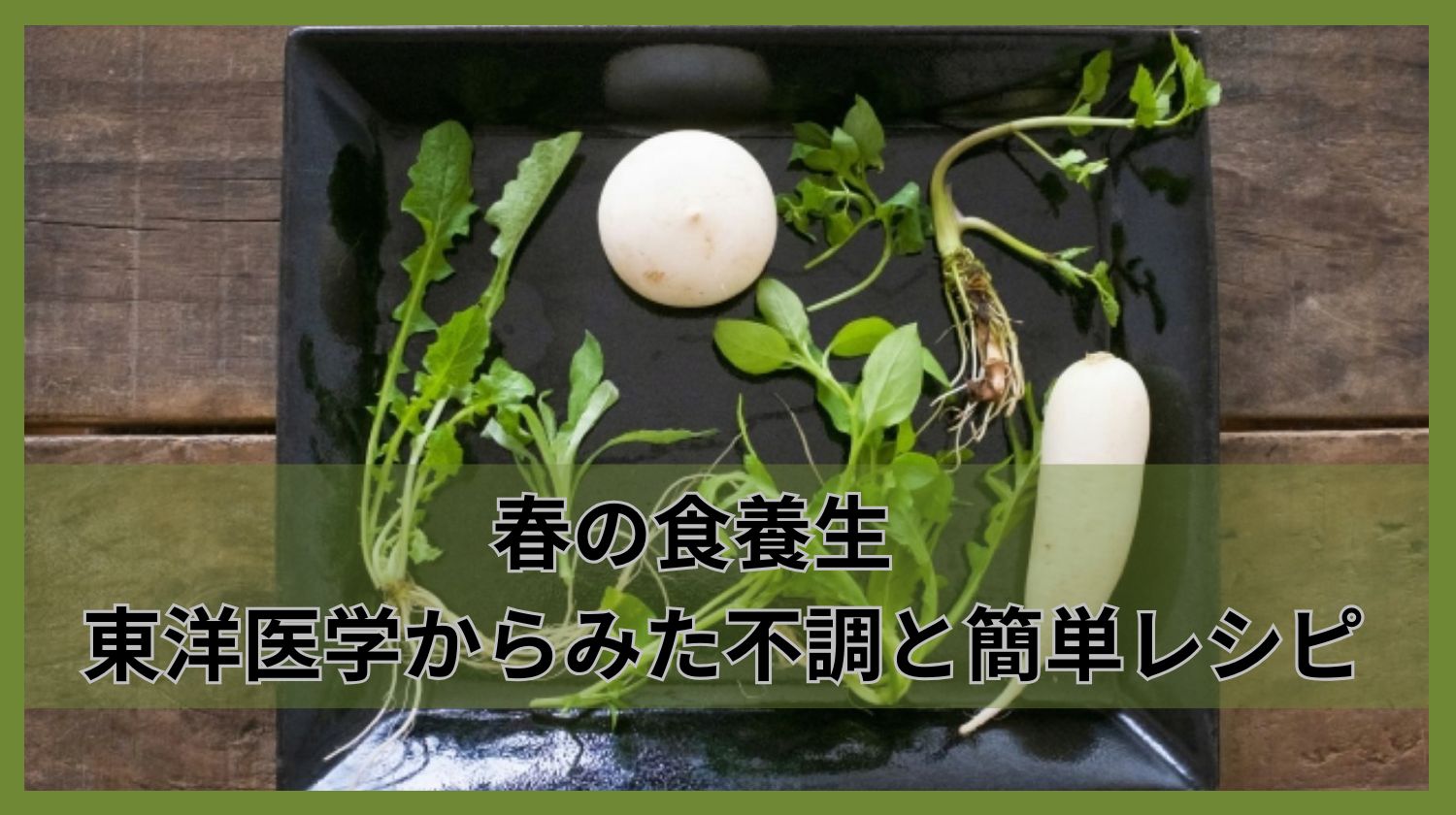春になると、なんとなく体がだるい、イライラする、花粉症がつらい…そんな不調を感じることはありませんか?
実はそれ、東洋医学でいう「春の不調」かもしれません。春は自然界だけでなく、私たちの体にも大きな変化をもたらす季節です。
特に東洋医学では、春は「肝(かん)」の季節とされ、気や血の巡りに大きな影響を与えると考えられています。
本記事では、春の不調を東洋医学の視点からアプローチし、春特有の不調をやさしく整える食べ方や、今すぐできるレシピをわかりやすくご紹介します。
身体も心も軽やかに過ごしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
春の食養生 初心者が知っておきたい「春の不調」とは?

春は寒暖差が大きく、自律神経が乱れやすい季節です。
さらに、東洋医学では春は「肝(かん)」が活発になる時期とされ、この肝の働きが乱れるとさまざまな不調が現れます。
肝は気や血の巡りを司る重要な臓器で、ここがうまく働かないと、イライラや目の疲れ、だるさ、アレルギー反応などが起こりやすくなります。
特に春の食養生には、この肝の調整が大切です。食事からやさしく体調を整えることで、春の不調を予防・改善することが可能です。
次の項目では、肝の働きと春の不調の深い関係について詳しく見ていきましょう。
春の不調が起きやすい理由|東洋医学の「肝」の働きと関係が深い!
東洋医学では、春は「肝(かん)」の季節とされ、肝の働きが活発になります。
肝は血を蓄え、全身に気を巡らせる重要な役割を担っています。
特にストレスや怒りといった感情は肝に影響しやすく、春はこれらの感情が高まりやすいとされています。
気温や環境の変化が大きい春は、自律神経が乱れやすく、肝の働きも不安定になりがちです。
その結果、気の巡りが滞り、イライラや不眠、肩こり、消化不良などの「春の不調」が起こりやすくなります。
春の食養生では、この肝をサポートする食材や生活習慣を意識することが大切です。
春に現れやすい代表的な症状|イライラ・目の疲れ・眠気・花粉症など
春になると、多くの人が感じるのが「なんとなく不調」。東洋医学では、これらは「肝」の乱れが原因と考えられています。
代表的な春の不調としては、イライラや情緒不安定、目の充血や疲れ、日中の強い眠気、さらに花粉症などがあります。
肝は目と深い関係があるため、春の肝の不調は視力にも影響します。
また、気の流れが滞ると、精神的にも不安定になりやすく、自律神経にも影響を与えます。
春の食養生では、こうした不調を穏やかに整えるために、旬の食材や調理法を活用することがポイントです。
東洋医学で考える春の食養生|初心者にもやさしい考え方

春の食養生では、「気(き)」「血(けつ)」「肝(かん)」のバランスを整えることが重要です。
東洋医学では、これらが滞ると体調が乱れやすくなるとされます。
特に春は肝が活発になる季節なので、肝の働きを助ける食材を積極的に取り入れることが、初心者でも始めやすい養生の第一歩です。
また、重たい食事よりも、軽くて消化の良いものを選ぶのが春のポイント。
「春の食養生 初心者向け」には、旬の野菜や香りの良い食材が適しています。
体内の気を巡らせ、心も体もスッキリさせる食べ方を心がけましょう。
「気」「血」「肝」を整えるとは?春に注目すべきバランスのとり方
東洋医学では、「気」はエネルギー、「血」は栄養、「肝」はそれらを巡らせる司令塔のような存在です。
春はこの「肝」の働きが強まりやすい半面、ストレスなどで乱れやすい時期でもあります。
気が滞れば疲れやすくなり、血が不足すれば肌荒れや冷えに繋がります。
初心者が「春の食養生」を実践する際は、まずは香りの良い春野菜で気の巡りを促し、鉄分やたんぱく質で血を補う食材を意識しましょう。
また、イライラや不眠の原因となる肝の乱れを防ぐために、酸味や緑色の食材も効果的です。
日々の食事で、気・血・肝のバランスを整えて春を元気に乗り切りましょう。
食材選びの基本|春に取りたい食材と避けたいもの
春の食養生では、旬の野菜や香味野菜、酸味のある食材が特におすすめです。
春キャベツ、菜の花、たけのこ、三つ葉などは気の巡りを助け、肝を穏やかに整えます。
また、酢や柑橘類などの酸味は、肝の働きをサポートし、イライラを和らげる効果があります。
一方で、脂っこいものや甘すぎるもの、冷たい飲食物は、気の巡りを妨げる原因になりますので、できるだけ控えるようにしましょう。
春の食養生では、食材選びを少し意識するだけでも、体調に大きな違いが出てきます。
自然のリズムに合わせた食事で、無理なく整えていきましょう。
初心者でも簡単にできる!春の不調対策レシピ3選

春の食養生で大切なのは、日々の食事に無理なく取り入れられることです。
ここでは、東洋医学の考えをもとに、肝をいたわり、気や血の巡りを整えるレシピを3つご紹介します。
どれも簡単な調理法で、旬の食材を活かした栄養バランスの良いメニューです。
イライラや花粉症、目の疲れが気になる方は、ぜひ今日から試してみてください。
毎日の食事を少し変えるだけで、体調にも気分にも嬉しい変化が現れますよ。
肝をサポート!菜の花とあさりのスープ
春が旬の菜の花と、ミネラル豊富なあさりを使ったスープは、肝をやさしくサポートしてくれる一品です。
菜の花は苦味と香りがあり、気の巡りを促す作用があるとされます。
また、あさりには鉄分やタウリンが豊富で、血を補い、肝の働きを助ける効果が期待できます。
作り方は簡単で、あさりを酒蒸しして出汁をとり、茹でた菜の花を加えて塩で味を整えるだけ。
シンプルながらも、春の食養生にぴったりの栄養たっぷりスープです。
食養生の初心者の方でも手軽に取り入れられ、体も心もほっと落ち着く味わいです。
気の巡りUP!春キャベツと新玉ねぎの蒸し煮
春キャベツと新玉ねぎは、どちらも春が旬の食材で、体内の「気」の巡りをスムーズにしてくれる働きがあります。
キャベツの甘みと玉ねぎのやさしい辛味が調和し、胃腸にもやさしい一品です。
作り方は、ざく切りにした春キャベツと薄切りの新玉ねぎを鍋に入れ、オリーブオイルと少量の水で蒸し煮にするだけ。
仕上げに塩とこしょうをふれば、素材のうまみが引き立つシンプルな養生料理になります。
食養生の初心者に最適で、気分が落ち込みやすい時にもおすすめです。軽やかな春の味わいが、心も体も前向きにしてくれます。
花粉症対策に!レンコンと鶏むね肉の薬膳炒め
花粉症に悩む方におすすめなのが、レンコンと鶏むね肉を使った薬膳風の炒め物です。
レンコンは粘膜を保護し、鼻や喉の不調を和らげる働きがあります。
鶏むね肉は高たんぱくで疲労回復を助け、「気」を補う作用があるとされます。
作り方は、薄切りにしたレンコンと一口大の鶏むね肉を、生姜とにんにくで炒め、塩麹や少量の醤油で味を整えるだけ。
体を内側から温め、免疫力もサポートします。春の食養生の初心者にもぴったりで、花粉症の季節を元気に乗り切る助けになります。
お弁当や夕食のおかずにもおすすめの一品です。
まとめ

春は「肝」が影響を受けやすい季節。東洋医学では、肝の乱れが心身の不調につながると考えられています。
春の食養生では、旬の食材を取り入れながら、気・血・肝のバランスを整えることが大切です。
今回ご紹介した3つの簡単レシピは、日々の食卓で気軽に実践できるものばかり。
春の揺らぎに負けない体づくりを、今日から始めてみましょう。