「高齢の家族が食事を残すようになってきた」「噛む力や飲み込む力が弱ってきて、メニューに悩む」
——そんなお悩みをお持ちの方にこそ知ってほしいのが、発酵食品を使った介護食レシピです。
発酵食品は、やわらかく加工しやすく、栄養価が高いことから、高齢者の健康維持にも大きな力を発揮します。
さらに、自然なとろみや旨みを引き出すため、塩分や添加物を抑えても、食事をおいしく仕上げることができます。
この記事では、やわらかくて嚥下しやすいメニューを3つ厳選してご紹介します。
毎日の食事づくりにすぐ使える実践的なレシピですので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 発酵食品を使った介護食レシピとは?やわらかくて食べやすい理由
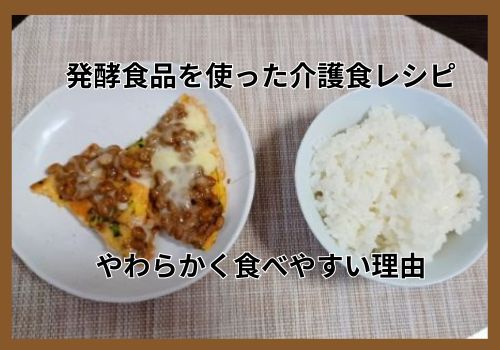
発酵食品を使った介護食レシピとは、納豆・塩麹・甘酒などの発酵食品を活用したものです。
そして、高齢者が「噛みやすく」「飲み込みやすく」「消化しやすい」料理に仕上げたものです。
発酵の力によって、食材が自然とやわらかくなるため、調理の手間を抑えながらも、体に優しい介護食を作ることができます。
発酵食品は、酵素や乳酸菌の働きで食材の繊維を分解し、素材の旨味を引き出します。
この分解作用により、食感がやわらかくなるため、噛む力が弱くなった高齢者でも無理なく食べられるのです。
また、嚥下(えんげ:飲み込み)のしやすさも向上し、誤嚥(ごえん)リスクの軽減にもつながります。
さらに、発酵食品には腸内環境を整える効果があり、便秘になりやすい高齢者にもおすすめです。
発酵食品を取り入れた介護食は、単に「やわらかい」だけでなく、味や栄養面でも優れた食事になります。
1-1. 介護食における「やわらかさ」と「嚥下しやすさ」とは
介護食において重要なのは、「やわらかさ」と「嚥下(えんげ)しやすさ」のバランスです。
やわらかさとは、噛む力が弱くなった高齢者でも負担なく噛める状態を指します。
一方で、嚥下しやすさとは、食べ物をスムーズに喉から食道へ送れることを意味します。
これらの要素は、食事の安全性と満足度に直結します。
高齢になると、咀嚼(そしゃく:噛む力)や嚥下機能が衰え、硬いものやパサついた食材は誤嚥や窒息のリスクを高めます。
そのため、介護食では「舌でつぶせる」「口の中でまとまりやすい」「とろみがある」といった特徴が求められます。
これにより、安全においしく食事を楽しめるのです。
例えば、食材を細かく刻んだり、加熱して柔らかくしたりする工夫は基本です。
それに加えて発酵食品を使うことで、自然にとろみが出たり、素材がやわらかくなるため、嚥下しやすいメニュー作りに役立ちます。
1-2. 発酵食品が介護食に向いている3つの理由
発酵食品は、介護食にとても適した食材です。その理由は大きく分けて3つあります。
1. 食材がやわらかくなる
発酵食品に含まれる酵素は、たんぱく質や繊維質を分解する働きがあります。
たとえば塩麹に肉を漬けると、自然に繊維がほぐれ、口当たりがやさしくなります。
この効果は、噛む力が弱い高齢者にとって大きな助けになります。
2. 自然な旨味で減塩・低添加が可能
発酵の過程で生まれるアミノ酸や乳酸菌が、深い旨味を引き出します。
そのため、調味料を多く使わなくても美味しく仕上がり、塩分制限が必要な高齢者にも安心して提供できます。
3. 消化吸収が良く、腸内環境を整える
納豆や甘酒、ヨーグルトなどの発酵食品には乳酸菌や酵母菌が含まれ、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。
高齢者に多い便秘の予防にもつながり、体の中から健康を支えます。
このように、「やわらかさ」「栄養」「旨味」という三拍子がそろっている発酵食品は、まさに介護食にぴったりな存在なのです。
1-3. 塩麹や甘酒など、高齢者におすすめの発酵食品とは
発酵食品の中でも、特に高齢者の介護食に向いているものがあります。
それが「塩麹」「甘酒」「納豆」など、やわらかくて栄養価が高い食品です。
塩麹(しおこうじ)
塩麹は、米麹に塩と水を加えて発酵させた万能調味料です。
食材に漬けると、たんぱく質を分解してやわらかくし、旨味もアップします。
塩分控えめでも味がしっかりつくため、減塩が必要な高齢者にも最適です。
甘酒(あまざけ)
砂糖を使わず、米と米麹だけで自然な甘みを引き出した「麹甘酒」は、飲む点滴とも呼ばれるほど栄養価が高い飲料です。
ビタミンB群やブドウ糖が豊富で、エネルギー補給にも役立ちます。
飲みやすく、ポタージュや煮物に加えると、自然なとろみも出て嚥下しやすくなります。
納豆
納豆は発酵の力で消化吸収が良く、たんぱく質やビタミンK、食物繊維も豊富です。
粘り気があるので飲み込みやすく、他の食材と混ぜてもまとまりやすいのが特長です。
ただし、においや味にクセがあるため、苦手な方には少量から試すのがおすすめです。
これらの発酵食品を介護食に取り入れることで、毎日の食事が楽しく、安全で、栄養バランスのとれたものになります。
2. 嚥下しやすいやわらか発酵レシピ3選【実践編】

ここからは、実際にご家庭で簡単に作れる「嚥下しやすい」「やわらかい」「発酵食品を活用した」介護食レシピを3つご紹介します。
すべて、発酵食品の持つ旨味や酵素の力を活かしたやさしい味わいのレシピです。調理の手間も少なく、栄養バランスにも優れています。
それぞれのレシピは、以下のようなポイントを意識しています。
ポイント
- 噛む力が弱くても安心のやわらか食感
- 喉ごしがよく、とろみやまとまりがある
- 発酵食品の栄養と風味で、おいしさと健康を両立
最初の一品は、納豆とじゃがいもを使ったやわらかお焼きです。
2-1. 納豆とじゃがいものやわらかお焼きレシピ
材料(2人分)
- じゃがいも:2個(約300g)
- 納豆:1パック
- 青ねぎ(刻み):大さじ1
- 片栗粉:大さじ1
- ごま油:少々
作り方
- じゃがいもは皮をむいて柔らかくなるまで茹で、熱いうちにつぶします。
- 納豆はよく混ぜて粘りを出し、付属のたれも加えます。
- つぶしたじゃがいもに納豆、刻んだ青ねぎ、片栗粉を加えてよく混ぜます。
- 手のひらサイズに丸めて、フライパンにごま油を少量ひき、弱火で両面をゆっくり焼きます。表面に焼き色がついたら完成です。
ポイントとアレンジ
・じゃがいもに含まれるデンプンで、まとまりやすく、喉ごしもなめらかです。
・納豆の粘りが自然なとろみとなり、嚥下しやすくなります。
・青ねぎの代わりに人参やしらすを加えると、彩りと栄養バランスがさらに良くなります。
2-2. 甘酒入りかぼちゃポタージュの作り方
甘みのあるかぼちゃと発酵食品の甘酒を組み合わせた、やさしい味わいのポタージュです。とろみがあるため嚥下しやすく、高齢者にも安心して食べてもらえる一品です。
材料(2人分)
- かぼちゃ(皮と種を除いたもの):200g
- 玉ねぎ:1/4個
- 無調整豆乳:200ml
- 麹甘酒(ストレートタイプ):100ml
- 塩:ひとつまみ
- オリーブオイル(またはバター):小さじ1
作り方
- かぼちゃは皮をむき、2cm角ほどに切ります。玉ねぎは薄切りにします。
- 鍋にオリーブオイルを熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒めます。
- かぼちゃを加え、水100ml(分量外)を入れて柔らかくなるまで煮ます。
- 粗熱が取れたら、豆乳・甘酒と一緒にミキサーにかけてなめらかにします。
- 再び鍋に戻して温め、塩で味を調えたら完成です。
ポイントとアレンジ
・麹甘酒の自然な甘さが、砂糖を使わずとも満足感のある味に仕上げます。
・豆乳で仕上げることで、動物性脂肪を控えたい方にも安心。牛乳でも代用可能です。
・ミキサーの使用が難しい場合は、フォークやマッシャーでつぶしてもOKです。
嚥下サポートのひと工夫
ポタージュのとろみは、飲み込みを助ける重要な要素です。
必要に応じて市販のとろみ調整食品を少量加えることで、さらに安心して食べられるようになります。
2-3. 塩麹でやわらかく煮る鶏むね肉のとろみ煮
鶏むね肉は高たんぱくでヘルシーですが、調理によってはパサつきがちです。
そこで、塩麹に漬けることで、やわらかくジューシーに仕上がります。
自然なとろみを加えることで、嚥下しやすくした介護食に最適な一皿です。
材料(2人分)
- 鶏むね肉:1枚(約200g)
- 塩麹:大さじ1.5
- にんじん:1/4本(細切り)
- 玉ねぎ:1/4個(薄切り)
- 片栗粉:小さじ1
- 水:200ml
- サラダ油:小さじ1
作り方
- 鶏むね肉は皮を取り、そぎ切りにして塩麹をまぶし、冷蔵庫で30分〜1時間漬け込みます。
- フライパンに油を熱し、鶏肉を弱火で焼き色がつくまで炒めます。
- にんじんと玉ねぎを加えて軽く炒め、水を加えて弱火で10分ほど煮ます。
- 火を止めて水溶き片栗粉(片栗粉小さじ1+水小さじ2)を加え、とろみをつけたら完成です。
ポイントとアレンジ
・塩麹の酵素がたんぱく質を分解し、鶏肉がしっとりとやわらかくなります。
・味つけは塩麹だけで十分。高齢者にも優しいまろやかな塩味です。
・にんじんや玉ねぎは細切りにして、煮込みでさらにやわらかくするのがコツです。
嚥下が不安な方には…
具材をミキサーにかけ、ポタージュ風にアレンジしてもOKです。とろみを強めに調整すれば、飲み込みがさらにスムーズになります。
3. 高齢者の食事に発酵食品を取り入れるメリットと注意点

発酵食品は高齢者の健康を支える強い味方です。腸内環境を整える効果や、消化のサポート、免疫力の向上など、多くのメリットがあります。
しかし、その一方で、体調や体質によっては注意も必要です。
この章では、発酵食品を取り入れるうえで知っておきたい利点と注意点を解説します。
3-1. 発酵食品が腸内環境や免疫力に与える影響
発酵食品には、乳酸菌や酵母菌、納豆菌などの有用な微生物が豊富に含まれています。
これらの善玉菌は、腸内の悪玉菌の増殖を抑え、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を整える働きがあります。
腸の健康は「第二の脳」とも呼ばれ、免疫力と密接に関係しています。
特に高齢者は腸内環境が乱れやすく、便秘や下痢、栄養吸収の低下などの問題が起こりやすいです。
発酵食品を継続的に取り入れることで、腸内の善玉菌をサポートし、排便リズムの安定や免疫機能の向上が期待できます。
甘酒に含まれるオリゴ糖や、納豆のナットウキナーゼといった成分も、腸を活性化させる栄養素として注目されています。
発酵食品は、単なる食品ではなく、自然な健康サポート食品といえるでしょう。
3-2. 高齢者に発酵食品を使うときに注意したいポイント
発酵食品は健康効果の高い食材ですが、高齢者に提供する際にはいくつか注意が必要です。
特に体調や薬の影響を受けやすい高齢者には、慎重な配慮が求められます。
1. 塩分に注意
味噌や醤油、塩辛などの発酵食品は塩分が多いものもあります。
高血圧や腎臓疾患のある方には、減塩タイプを選ぶか、使用量を控える工夫が必要です。
塩麹も発酵食品ですが、少量で十分に味が出るため、上手に使えば減塩効果にもつながります。
2. 消化機能との相性を確認
一部の発酵食品(キムチやチーズなど)は脂肪分や刺激が強いことがあります。
胃腸が弱い高齢者には避けた方がよい場合も。甘酒や納豆、塩麹のように消化がよく刺激の少ないものから取り入れると安心です。
3. アレルギーや薬との相互作用
納豆に含まれるナットウキナーゼは血液をサラサラにする働きがあります。
抗凝固薬(ワーファリンなど)を服用中の方は、納豆の摂取を避けるよう指導されることがあります。
食材の成分と服薬内容との関係は、事前に医師や管理栄養士に確認しましょう。
4. 温度・保存管理も重要
発酵食品は生きた菌が多く含まれているため、保存温度の管理が重要です。
常温保存が可能なものでも、夏場などは冷蔵庫での保管がおすすめです。
このように、発酵食品は高齢者の健康に役立つ一方で、状況によっては負担になることもあります。個々の体調に合わせた使い方が大切です。
3-3. 介護食に発酵食品を活用する際のコツとアレンジ法
発酵食品はそのまま使うだけでなく、調理法や組み合わせ次第で、よりおいしく・安全に・楽しく取り入れることができます。
ここでは、介護食に発酵食品を活用する際の具体的なコツとアレンジ法をご紹介します。
1. 自然なとろみを生かす
甘酒や納豆などの発酵食品は、自然なとろみや粘りがあり、嚥下サポートに効果的です。
市販のとろみ剤に頼らずに済む場合もあり、自然な口当たりで食事の楽しみを損なわずに済みます。
2. 下ごしらえに活用して食材をやわらかくする
塩麹やヨーグルトは、肉や魚の下味として使うと、酵素の働きで繊維が分解され、加熱後もふっくらやわらかに仕上がります。
食べやすさだけでなく、味に深みが出るため、少量でも満足感が得られます。
3. 毎日のメニューに少しずつ取り入れる
毎食に無理なく取り入れるには、少量から始めるのがポイントです。
朝食に甘酒入りスムージー、昼に納豆入りの和え物、夜に塩麹漬けの肉や魚料理など、バランスよく活用しましょう。
4. 発酵食品+旬の野菜で栄養バランスUP
発酵食品に季節の野菜を組み合わせることで、栄養の幅が広がります。
例えば、春は菜の花の塩麹和え、秋にはかぼちゃの甘酒煮など、旬の素材と発酵食品を組み合わせることで、彩りや味の変化も楽しめます。
5. 苦手な発酵食品は他の味でアレンジ
発酵食品特有のにおいや味が苦手な方には、出汁やハーブ、柚子などを加えて風味を調整すると食べやすくなります。
無理に取り入れるのではなく、好みに合わせた工夫も大切です。
まとめ

昔は、意識しなくても自然と摂れていた発酵食品ですが、やわらかく、嚥下しやすくすることで優れた介護食になります。
注意点を守りながら、日々の食卓に少しずつ加えていくことで、高齢者の健康と食の楽しみを支えることができるでしょう。
